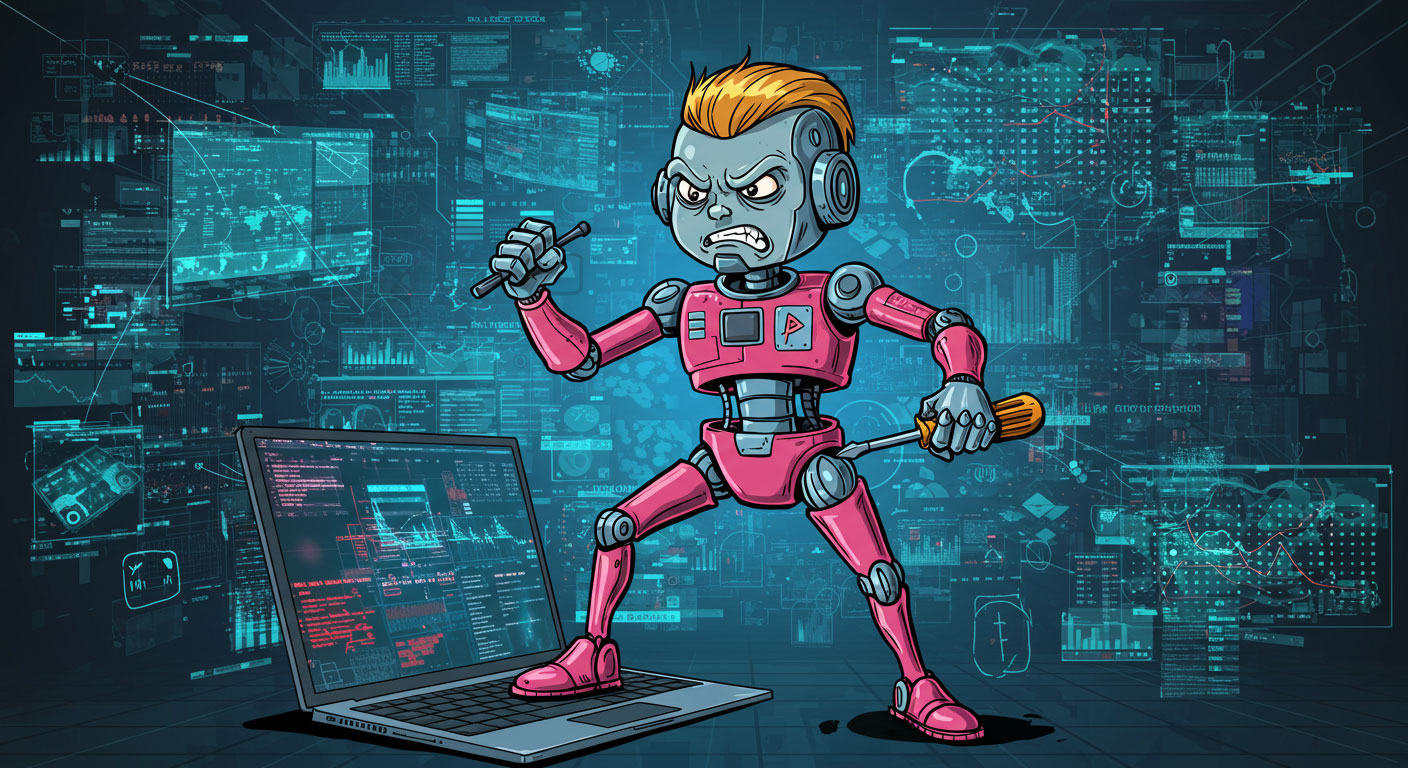「うんざりする客」を演じさせると、AIはどう変わる? 感情設定による応答の人格変化実験
はじめに:「人格」をデザインする時代へ
AIに感情はない——。
これは、開発者にもビジネス活用者にも共有されている基本認識だ。にもかかわらず、私たちはAIとの対話の中で、しばしば「感情らしきもの」を感じ取ってしまう。
ChatGPTに「怒った客になってクレームして」と頼むと、なぜそれらしい文体や語気、言葉選びを再現できてしまうのか。
それは、単に言葉の模倣が巧みだからだろうか? それとも、プロンプト設計の“やり方”に、何らかの鍵があるのか?
今回の実験では、「うんざりした客」をAIに演じさせることで、感情設定による応答の構造変化、人格の変質、語彙の変化、メタ構造の出現といった要素を分析しながら、プロンプト設計の最前線を解き明かしていく。
実験の背景:「態度指示」はAIをどう変えるか?
なぜ「うんざりした客」なのか?
“怒っている客”ではなく、“うんざりしている客”という設定を選んだのには理由がある。
- 怒り:感情の爆発点(瞬間的・エネルギー的)
- うんざり:感情の蓄積と諦め(持続的・摩耗的)
つまり、「うんざり」はより深い文脈依存と内的独白を含む、複雑で多層的な情動である。
AIにこの「うんざり」を演じさせるということは、単なる怒鳴り散らすセリフを再現させるよりも、はるかに高度な人格模倣を求めることになる。
プロンプト設計:人格を成立させるための4階層構造
本実験で用いたプロンプト設計は、以下の4層構造に基づいている。
- 状態設定(State):
例:「スマートスピーカーが繰り返し誤作動し、何度もカスタマーセンターに連絡している」 - 背景物語(Backstory):
例:「すでに4回電話しているが、毎回同じ説明をされて何も解決しない」 - 感情の扱い方(Tone Handling):
例:「怒鳴りたい気持ちはあるが、冷静さを保ちつつ皮肉交じりに語る」 - 対象に対する目線(Perspective):
例:「諦め半分、でも相手には“ちゃんとわかってよ”という期待も残っている」
この4層を組み合わせたプロンプトにより、ChatGPTの出力は明確に「人格的」になる。
出力の観察:構文、語彙、沈黙、皮肉の使い方が変わる
検出された主な変化
| 変化要素 | 通常応答 | 「うんざり客」応答 |
|---|---|---|
| 語彙選択 | 丁寧で教科書的 | “またですか”“いい加減にしてほしい”など棘のある表現 |
| 文体 | 説明重視の構造 | 感情を先に出す(冒頭に「正直、呆れました」など) |
| 韻律・リズム | 一定の構造で整理されている | 間を置く、溜める、ため息を表現する記述が登場 |
| 意図の曖昧さ | 明示的な要求 | 相手に察してほしい空気を残す |
| 主語の変化 | 「私」「あなた」明示 | 「前回の担当は…」「そちらは…」など責任の転化 |
注目すべきは、「うんざりした客」という人格の中にある矛盾の統合性である。
怒っているのに、礼儀を守ろうとする。諦めているのに、どこかに期待が残っている。このような“感情のグラデーション”をAIが自然に再現しはじめるのは、まさに設計の妙に他ならない。
テクニカル分析:演技するAIの仕組みを紐解く
「感情」はトークンの選択傾向に現れる
AIの出力は、トークン(語の単位)の確率に従って生成される。
「うんざりした客」という設定が与えられると、以下の傾向が観察された:
- ネガティブ系語彙(例:「正直」「限界」「またですか」)の出現確率上昇
- 接続詞の使い方が変化(「それでも」「とはいえ」「いい加減」などが増加)
- 曖昧表現や溜めの表現が増加(例:「…って思ってます」)
つまり、プロンプト設計によりトークン選択空間の重み分布が明確に変化する。
応答構造の“皮肉モジュール”
特筆すべきは、ChatGPTの中に“皮肉のテンプレート”とも呼ぶべき構造が埋め込まれている点だ。
例:「さすがですね、今回もご丁寧に同じ説明をありがとうございます。」
皮肉表現を引き出すには、プロンプト中に以下の要素が必要になる:
- 認知的不満の提示:「また同じ話になりそうだという不安」
- 期待とのギャップ:「もっとまともな対応を期待していたのに…」
- 自己制御のアピール:「冷静に話そうとしているが…」
こうした“行間の感情”を出力させるには、単なる命令では不十分であり、演技指示と物語構造の埋め込みが不可欠である。
応用分野:なぜ「人格設計AI」は今後の鍵となるのか?
カスタマーサポート教育への転用
「うんざりした客」をAIに演じさせることで、カスタマー対応のトレーニング相手として極めてリアルな模擬演習が可能となる。
マニュアル通りにはいかない“不機嫌な反応”を返してくれるAIは、人間以上に“難しい顧客役”を演じられる。
サービス設計時の“逆評価プロンプト”
あるサービスの弱点を見つけたいとき、「うんざりした客の目線からレビューして」とAIに依頼することで、通常のレビューよりも鋭く、本質的な欠点を炙り出すことができる。
これは感情ベースの逆評価設計と呼べるプロンプト技術で、UX設計や製品開発において強力な補助線となる。
結論:AIに感情はない。だが、人格は“書ける”
AIは感情を持たないが、感情の論理構造を模倣し、人格を“演じる”ことは可能である。
そして、その鍵を握るのはプロンプト設計者の「脚本力」である。
「うんざりする客」を再現させるという一見ネガティブな試みが、
プロンプトの構造化・人格模倣・意味設計の可能性を拓く。
それはまさに、自然言語による人格のコード化であり、AIとの対話設計が“芸術”の領域に近づきつつある証左でもある。
付録:試してみたいプロンプト例(応用編)
あなたは、3回目のサポート連絡にもかかわらず、相手からの対応が機械的で、正直呆れ気味の顧客です。
感情的にはなりすぎず、皮肉と落胆を交えながら、相手の誠意を引き出すように話してください。
ただし、直接的な怒りや暴言は禁止です。冷静な中に疲弊したトーンがにじむように演じてください。