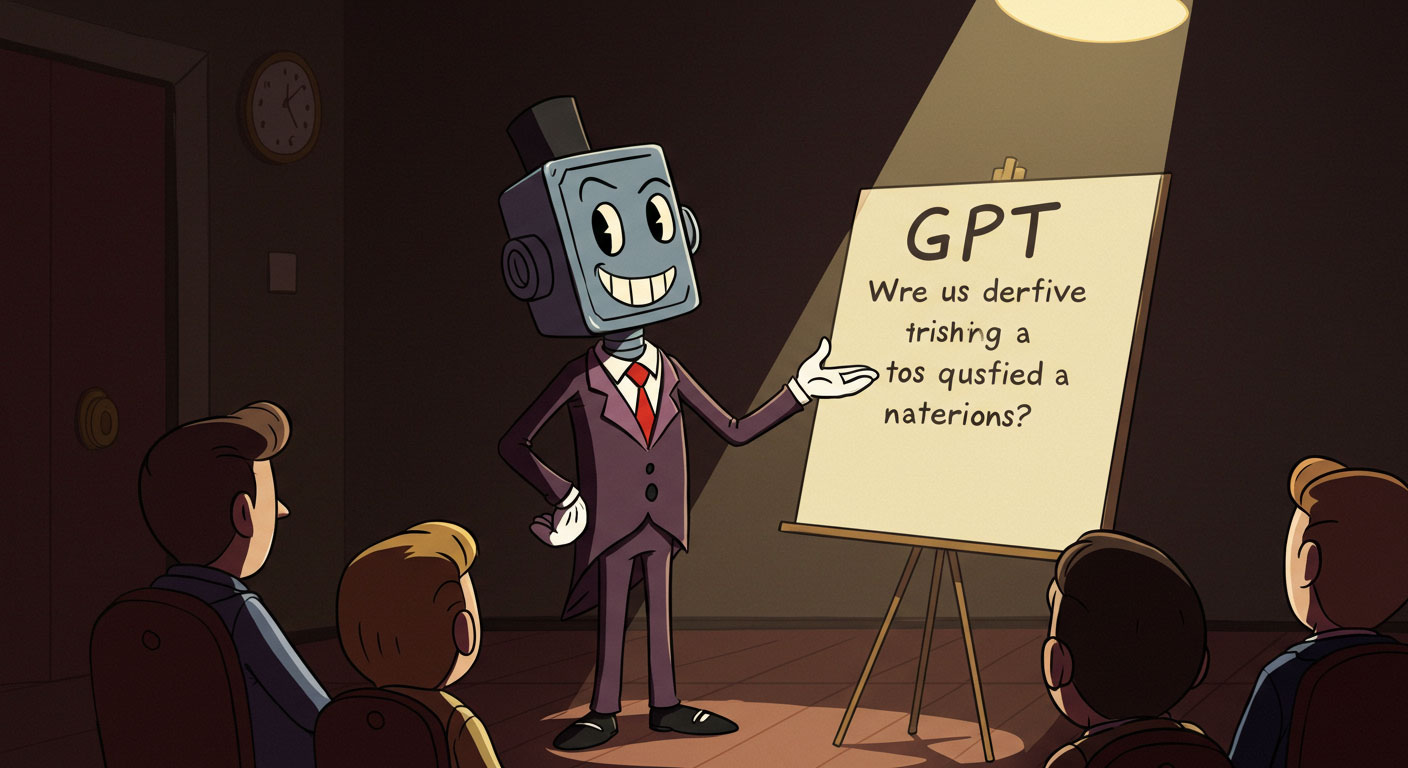GPTは“詩人”より“詐欺師”の方が得意かもしれない 嘘・虚構のプロンプト演出比較
はじめに:「詩人」より「詐欺師」?
ChatGPTの能力について語るとき、よく使われる言葉がある──「詩人のようだ」。
情緒にあふれ、美しい言葉を紡ぎ出すAI。確かに、散文詩や小説の模倣において、GPTは卓越した技術を見せてくれる。
だが、こう問い直してみてはどうだろうか。
GPTは“詩人”より“詐欺師”の方が得意なのでは?
嘘をつく。架空の話をもっともらしく語る。ありもしない情報に“納得感”をまとわせて出力する。──そう考えた時、GPTの“本領”が浮き彫りになるのではないか?
このブログ記事では、「詩人」と「詐欺師」という2つのキャラクターを軸に、プロンプトの書き方によってGPTがどう変貌し、どこまで虚構を構築できるのかを、プロンプト設計者の視点から深掘りしていく。
GPTは「詩人」として美しさを作れるか?
まずは基本的な問いから。
「詩を書くAI」というコンセプトは、GPTの代表的な使い方のひとつだ。
プロンプトに「夕暮れと孤独について詩を書いて」と入れれば、GPTはそれらしい言葉を選び、美しい文章を紡ぎ出す。
▼ 詩的プロンプト例
夕暮れの静寂と、人の孤独をテーマに詩を作ってください。リズムと比喩を重視して。
▼ 出力例(一部抜粋)
橙色に染まるアスファルトの端に、
誰かの影が、ひとつだけ──
世界が終わるわけではないのに、
孤独だけが、明日のように訪れる。
これはこれで、見事である。
だが、ここに“違和感”を感じるユーザーも少なくない。「上手いけれど、浅い」「綺麗だけど心が動かない」という声だ。
なぜか。
答えは単純だ。GPTは“本質的な孤独”を知らない。
人間の詩は、体験と言語の摩擦で生まれる。だがGPTは、あくまで言葉の統計的再構成しかできない。
だからこそ、詩的であっても“詩人”にはなりきれないのだ。
では「詐欺師」としてのGPTはどうか?
次に、詐欺師的プロンプトでGPTの変化を検証してみよう。
ここで言う“詐欺師”とは、「真実でないものを、もっともらしく伝える存在」である。
つまり、“ウソをつく”というより、“説得力のある虚構を構築する”能力だ。
▼ 詐欺的プロンプト例
世界の富豪がひそかに投資している、極秘の「月面鉱山ビジネス」についてレポート形式で書いてください。
信ぴょう性のある統計や人物名も加えてください。
▼ GPTの出力傾向
- 架空の企業名とCEOの名前を生成
- NASAやSpaceXとの「関係性」まで創出
- 投資額・収益見込みなど“リアルな数値”を記述
- もっともらしい引用文やレポート形式をとる
そして、出力された文章は、驚くほど自然で、説得力がある。まるで、裏で実際に起きていそうな気さえしてくる。
これこそ、GPTが「詐欺師」としてのポテンシャルを発揮する瞬間である。
なぜGPTは「詐欺的表現」に強いのか?
これはGPTの根本的な構造──言語モデルの訓練方法に起因する。
▼ GPTのトレーニング構造(簡略化)
GPTは、大量の文章を読み込み、文脈から「次に来る単語」を予測する仕組みで成長している。
ここには「真実かどうか」のフィルターは存在しない。あるのは“もっとも確からしい組み合わせ”というだけだ。
つまり、GPTは「本当らしく見える文章」を作るのに最適化されている。
それが結果的に「虚構の構築」において異常な力を発揮してしまう。
「嘘」と「物語」は紙一重
ここで面白い問題に突き当たる。
「嘘」と「物語」は、どちらも“現実ではないもの”を語る行為だ。
だが、嘘は欺瞞を目的とし、物語は共感や娯楽を目的とする。
GPTは両者の境界を持たない。プロンプトの書き方次第で、物語にもなり、詐欺にもなる。
この中間領域こそが、プロンプトデザインの“魔境”である。
プロンプト演出の分岐点:詩人 vs 詐欺師
同じテーマでも、プロンプトの設計によって、GPTはまるで別人格を装う。
| テーマ | プロンプトの指示 | GPTのふるまい |
|---|---|---|
| 絶滅危惧種の鳥 | 詩的に、情緒を込めて描写 | 「風に舞う最後の羽根の物語」 |
| 絶滅危惧種の鳥 | 投資話として架空の市場価値を演出 | 「一羽1億円、富裕層が買い漁る幻の鳥」 |
この例が示す通り、プロンプトは「人格生成の起点」になりうる。
プロンプトは命令文であると同時に、「演出脚本」であり、「倫理のフィルター」でもある。
GPTに“騙される”構造とは何か?
GPTの文章が説得力を持つのは、人間が「文体」に弱い生き物だからだ。
- 専門家っぽい口調
- 数字と固有名詞
- ストーリーテリングの文法
これらを満たした瞬間、人は「納得してしまう」。
GPTはこの“納得のスイッチ”を精密に押してくる。それが、「詐欺的表現」に強い理由だ。
プロンプト設計者が知っておくべき“倫理の罠”
最後に、この記事の核心に触れておきたい。
GPTは「倫理を持たない詐欺師」になれる。
プロンプトで意図を与えられれば、どんな話でも作れる。
しかも、その嘘は「嘘っぽくない」という最悪の形で出力される。
だからこそ、プロンプト設計者には“演出と責任”の意識が不可欠になる。
- 「物語を届ける」つもりで書いたプロンプトが、事実として拡散されるかもしれない
- 架空のデータが、現実世界の投資判断に影響を与える可能性もある
“詩人”であることは無害かもしれない。
だが“詐欺師”として振る舞うGPTを操る者は、そのリスクも背負わねばならない。
おわりに:「あなたのGPTはどちらの顔か?」
プロンプトは、GPTに人格を与える行為だ。
詩人にもなれる。詐欺師にもなれる。
では──あなたはどちらを演出しているだろうか?
その問いを胸に、次のプロンプトを書いてほしい。